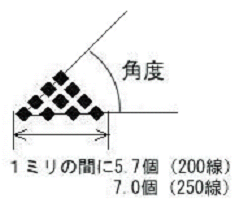
第2部 グラビアスクリーンの収集
1.グラビアスクリーンの基礎知識
目打の場合と同様に、まずはこの時代の記念切手のグラビアスクリーンについて、基礎知識をまとめておきます。以下の各章の記事では「角度」のバラエティに話を限定していますが、 この項では「線数」にも言及しておきましょう。
(1) グラビア印刷のミクロな姿
戦後記念切手の主流をなすグラビア印刷では、肉眼では見えないほどの小さな点々を網目状に規則正しく並べることによって、図案を表現しています。1つ1つの点(セル)の濃度や大きさを少しずつ変化させれば、階調豊かな表現が実現できます。また色の異なる点々を組合せれば、わずかな色数のインクによって微妙な中間色を表現することができます。多色刷りの印刷物を作るのに大変適した方法と言えます。
この点々の集合をグラビアスクリーンと呼びます(注)。その基本要素はセルの形状、間隔、並んでいる方向ですが、形状が問題になることはほとんどありません。間隔は1インチ(=約25ミリ)あたりのセルの数によって、「200線」とか「250線」のように表現します(線数)。方向は、セルの並び方向が切手印面の左右方向に引いた基線となす角度で表現します。
昭和末期頃までのグラビア切手では、1個1個のセルの形状は正方形で、それが正方格子の形に並んでいます。このような正方スクリーンの場合、スクリーン角度は0から90度までの数値で表すことができます。0度は90度と同じですが、90度と表記するのが普通です。
(注)
スクリーンとは、本当はそのような網目状の印刷をするための版面を作るのに使う道具のひとつに対する呼称なのですが、便宜上その版面で印刷された網目のこともスクリーンと呼びます。
(2) 線数・角度の測定方法
この網目を観察するには、もちろん切手の像を拡大しなければなりません。ルーペを使うのが昔ながらの一般的方法ですが、最近ではスキャナとパソコンで測定するのも大変有効な方法です。正方スクリーンの場合、線数は下図のように対角線方向で図るのが便利です。
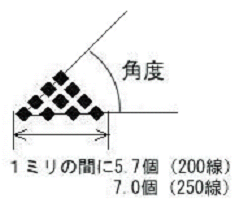
ルーペを使う場合、角度が90度であるか45度であるかといったあたりのことは、網目が見える限りは簡単に判別できますが、角度や線数を数値で知りたい場合は、長さや角度のスケールが組み込まれたルーペを使う必要があります。しかしその測定を正確に行うのはなかなか難しいもの。特に測定したい色が印面の中央部分に、しかも小面積でしか使われていない場合は、印面の端を基線として利用できないので、上図のようにしてルーペの視野内でスケールを合わせることができません。
このような場合は、スキャナを使ってパソコンに画像を取り込み、グラフィックソフトを使ってスケールを合わせることになります。使用するグラフィックソフトと読み込み解像度に合わせて、一度次図のような1ミリ間隔のスケールを作っておけば、読み込んだ画像にこのスケールを合わせることにより、正確に線数を測定することができます。角度測定の場合は、グラフィックソフトの機能を利用して指定角度だけ傾いた直線を引き、画像上のセルの並びと一致するかどうかを調べるという作業を、充分一致するまで繰り返します。
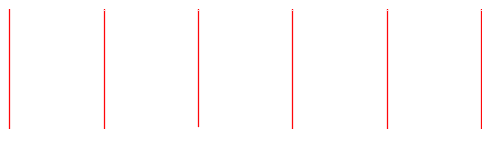
スキャナの解像度は2400dpi以上必要ですが、近年はこのクラスのスキャナも、ショップで簡単に購入することができます。スキャナで読み込んで測定する方法の欠点はただ一つ、測定に手間がかかることです。切手屋さんの店先で測定するわけにはいきません。ルーペで見て、あるいはスクリーン以外の色調などの要素でおおよその目星をつけて入手した切手を、あとからゆっくり調べるということになります。
現実問題としては、その切手に使われている全色のスクリーンが鮮明に観測できるということはめったになく、スキャナとパソコンを使っても線数や角度を全色精密に確定させるということは困難なものです。スクリーンが鮮明に見える切手はとても貴重な場合があります。
(3) 昭和時代の記念切手のグラビアスクリーン
昭和30年代初頭までの単色刷りの時代は、普通切手も含め正方スクリーンで、スクリーン角度はほぼ例外なく45度です(◆)。ルーペで拡大してみると、次の画像のように見えるはずです。
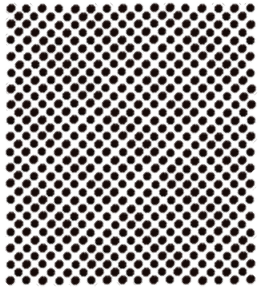
この場合、スクリーン線数は切手印面の四辺に現れる点々を(2)の説明図のようにして観察するのが便利です。印面のスクリーンが明瞭に見えない場合でも、印面周囲では見えることが多いものです。1列だけでも見えれば、線数の測定に役立てることができます。
スクリーン角度は、45度ではなく90度にする方が単純でスッキリするような気もしますが、この45度という角度が選ばれたのには理由があります。それは、多少角度がずれても印面の端が見苦しくならないからです。90度スクリーンの場合に角度が少しずれるとどうなるかは、「アジア大会14円」の章をご覧ください。
現在の平成時代のグラビア切手では、横または縦に伸びた菱形になっている菱形スクリーンが主流で、収集上いろいろと面白いことがありますが、これについては別の機会に譲ることとします。また網目の間隔(線数)も、普通切手の場合は製造時期を判別する上できわめて重要な分類要素になりますが、この部屋で取り上げる昭和30年代の記念切手については、ほとんどの切手が260線でバラエティはありません。以下ではスクリーンの角度に絞って、話を進めたいと思います。
(4) 多色刷り切手のスクリーン角度
昭和30年代に入って多色刷り切手が登場した際、異なる色のスクリーンを同じ角度にするとモアレと呼ばれる現象が発生して、仕上がりが汚くなると信じられていました。例えば下図のように黄色の網目(画面で見やすくなるように、黄色の色調を少し変えました)を印刷して、その上に青の網目を重ねるとき、Aのように網点が重ならないように印刷すれば、目には青と黄色が混ざって緑に見えますが、もしちょうど半周期分ずれてBのようになると、青インクが黄色を遮蔽して、(多少は濁った)青色に見えるでしょう。2色のスクリーンの相対位置を正確に管理することは事実上不可能なので、2色の重なり方の偶発的なずれによって、仕上がりはかなり異なったものとなってしまいます。
またその際、もし両者のピッチが少しずれてしまうと、Cのように重なる場所と重ならない場所が繰り返されることになります。結果として汚い縞模様が見えることになります。これがモアレ現象です。もともとの点の間隔の差が肉眼では見えない程度で微少なものであっても、C図の矢印で示される縞模様の周期は、2色のピッチのずれが小さければ小さいほど長くなり、1ミリとか2ミリというような、目に見える縞模様となってしまうのです。また2色のスクリーンの角度が少しずれた場合にも、同様の現象が起こります。
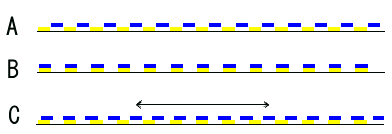
余談ですが、このような現象は2つの網目が同色の場合には、明暗の縞模様として現れます。身近な例としては、網戸に使う網を2枚重ねることによっても体験することができます。またこのような現象は網目を重ねる場合だけでなく、この網目をスキャナで読み取る場合にも生じます。スキャナの解像度をグラビアスクリーンのピッチと近い値にしてグラビア印刷を読み取ると、読み取った画像に汚い縞模様が現れることがあります。WeB上のサイトに掲載されている画像には、時としてこのような汚い縞模様が見られます。
このような現象を避けるには、2色の網点が「ほぼ同方向」に並ぶのを避けるのが、最も簡単な方法です。すなわちグラビア印刷の場合は、2色の角度を大きくずらせばよいわけです。ということで昭和30年代に登場したグラビア多色刷り切手では、モアレ現象を避けるため、それぞれの色のスクリーン角度を大きく変えて印刷するという手が使われました。印面の端まで使われている主色は45度、2色目は90度、3色目以降は60度とか、さらに半端な角度に設定されているのが普通です。しかしこの角度設定、特に3色目以降については、目分量でエイヤッと作業したようで、基準角度からかなりのずれが見られることがあります。版面を作り直したりした場合は、使われた版ごとに角度が少しずつ異なっているというような例もあります。
個々の切手についてどのような角度がどのように使われているかを調べるのは、なかなか大変な(しかし楽しい)作業です。普通切手の場合は結果が日専に詳しく記録されていますが、記念切手の場合は全くデータがありません(◆)。しかしこれを調べていくと、同じ切手でもスクリーン角度のバラエティが存在する切手が、わずかですが存在することに気づきます。このあたりの実情を、以下の個別記事の中で取り上げたいと思います。
しかし後になって、このようなモアレ現象は、切手のグラビア印刷の場合は実際上ほとんど問題にならないことが判明し、昭和40年代になると多色刷りの切手もすべての色のスクリーンを45度に統一するようになりました。その後昭和50年代の末期に「菱形スクリーン」が登場するまでの間、日本のグラビア切手では普通切手も記念切手も、すべての色を45度のスクリーン角度で印刷する時代が続きました。切手ごとにさまざまなスクリーン角度が用いられたことは、昭和30年代のグラビア記念切手の大きな特徴と言えるでしょう。
◆追記
新刊のV日専には、封書10円時代の記念切手について、現時点で確認されている角度バラエティのほとんどすべてが掲載されています。さらに今回のV日専の採録範囲外の単色刷り切手の中には、スクリーン角度が45度から数度ずれていて、しかも同じ切手にその角度のバラエティが存在する例も、わずかながら見つかっています。